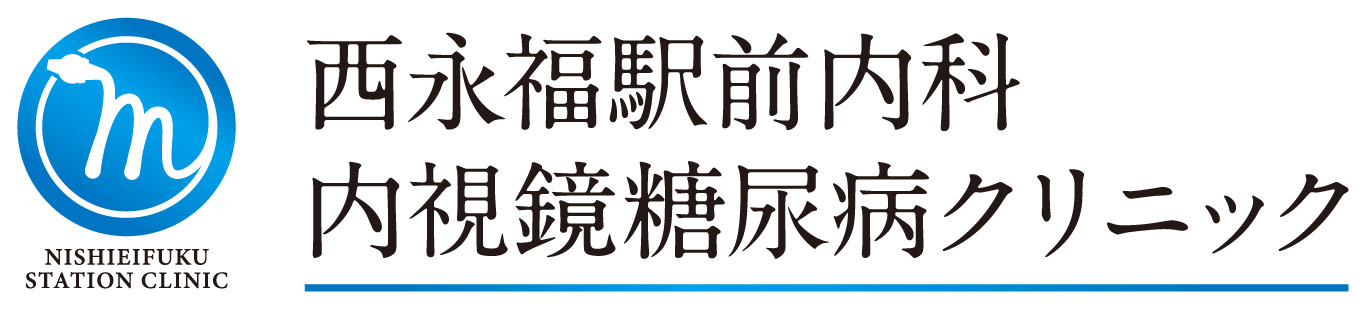肝臓内科とは
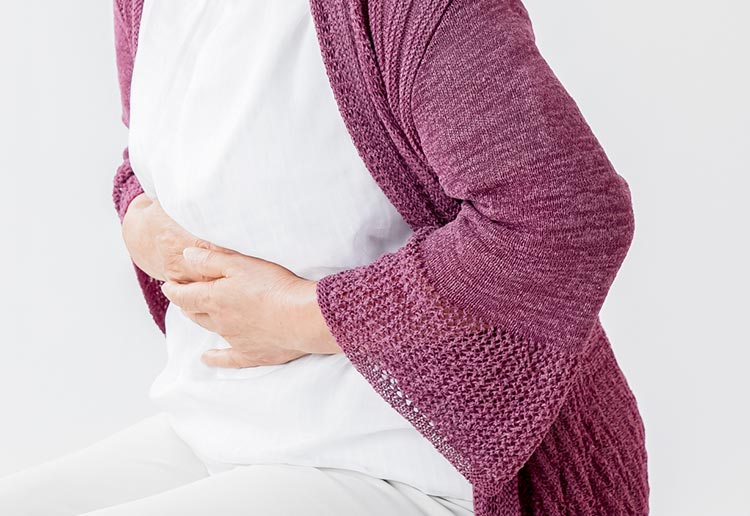
肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、病気が進行するまで自覚症状が現れにくい臓器です。そのため、健康診断で異常を指摘された場合や、肝機能が気になる方は早めの受診が重要です。肝臓病は慢性的に進行するものが多いため、適切な診断と治療で病気の進行を抑え、生活の質を維持することが大切です。
当院では日本肝臓学会認定
肝臓専門医・指導医の院長が、より専門性の高い診療をクリニックにて行っていきます。より高度な医療環境が必要と判断しましたら、大学病院などの医療機関と連携して治療を行っていきますので、健診等で肝障害を指摘された場合は、お早めにご受診ください。
健康診断で肝機能異常(AST、ALT、γ-GTPの上昇)を指摘された場合、症状がなくても、お早めに肝臓内科を受診することをお勧めします。
肝臓内科(当院)では、主に以下のような肝臓や関連臓器の疾患を診療します
- 脂肪肝・非アルコール性脂肪肝炎(MASH)
脂肪肝は過剰な脂肪が肝臓に蓄積した状態で、放置するとMASHに進行し、肝硬変や肝がんの原因になることがあります。 - ウイルス性肝炎
B型肝炎やC型肝炎などのウイルス感染による肝炎で、慢性化すると肝硬変や肝がんのリスクが高まります。 - 原発性胆汁性胆管炎(PBC)、自己免疫性肝炎
自己免疫の異常によって肝臓が攻撃される病気で、進行すると肝硬変になることがあります。
肝臓内科で行う検査
肝臓の病気を診断するために、以下のような検査を行います。
血液検査
AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ビリルビン、アルブミン、HBV・HCV抗体などを調べ、肝機能や炎症、ウイルス感染の有無を確認します。
腹部超音波検査(エコー検査)
肝臓の大きさや形、脂肪肝の有無、腫瘍や胆石の有無を調べます。放射線を使わないため、安全に行える検査です。
線維化評価検査(エラストグラフィ)
肝硬変の進行度を非侵襲的に調べるために行われる検査です。右脇腹の表面に振動と超音波を伝える特殊な「プローブ」をあて、その振動と超音波の伝わり方から肝臓の硬さや肝臓の脂肪量を測り、線維化の進行度を評価します。
肝臓内科で行う治療
肝臓の病気に対する治療は、原因に応じて異なります。例として、以下のようなものがあります。
ウイルス性肝炎の治療
B型肝炎には抗ウイルス薬を用いてウイルスの増殖を抑えて肝炎が起こらないようにします。C型肝炎にはインターフェロンフリーの経口薬が用いられ、ウイルス排除を目指します。
脂肪肝・MASHの治療
食事療法や運動療法を中心に、生活習慣の改善を行います。必要に応じて、糖尿病や脂質異常症の治療薬を使用します。