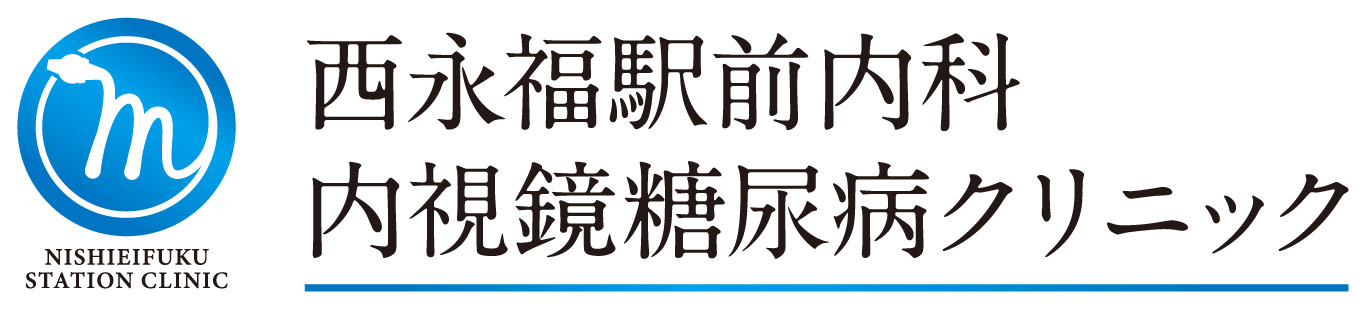消化器内科とは

消化器内科は、食べ物の消化や吸収を担う消化管(食道・胃・小腸・大腸)と、代謝や消化液の分泌などの働きを持つ肝臓・胆のう・膵臓といった臓器の病気を専門に診療する診療科です。消化器の病気は、軽い不調から重大な疾患まで幅広く、また原因も様々で、慢性的な症状が続くことも少なくありませんが、適切な診断と治療を受けることで、症状を改善したり、病気の進行を防いだりすることにつながります。
当院では、日本消化器病学会 専門医、日本肝臓学会 専門医・指導医である院長が、地域にあって、消化器病に関し専門性の高い診療を行っていきます。
以下のような症状がみられましたら、当院の消化器内科をご受診ください
- 胃もたれや胸やけ
- 腹痛
- 吐き気や嘔吐
- 食欲不振
- 便秘や下痢
- 体重減少
- など
上記以外でも、気になる症状がある場合はお気軽にご相談ください。また、健康診断などで肝機能異常、便潜血反応陽性、ピロリ菌陽性などが指摘された場合も、お早めにご相談ください。
消化器内科で扱う主な疾患には以下のようなものがあります
- 消化管(食道・胃・小腸・大腸など)の主な疾患
-
- 逆流性食道炎
- 食道カンジダ症
- 急性胃炎
- 慢性胃炎
- ストレス性胃炎
- 胃潰瘍
- 十二指腸潰瘍
- ピロリ菌感染症
- 機能性消化管障害(過敏性腸症候群(IBS)、機能性ディスペプシア など)
- 感染性胃腸炎
- 急性腸炎(虫垂炎、憩室炎、虚血性腸炎など)
- 慢性便秘
- 慢性下痢
- 炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎)
- ポリープ(胃・大腸)
- 食道がん
- 胃がん
- 大腸がん など
- 肝臓・胆のう・膵臓の主な疾患
-
- 脂肪肝
- 急性肝炎
- 慢性肝炎
- 肝硬変
- 胆石
- 胆嚢炎
- 胆嚢ポリープ
- 急性膵炎
- 慢性膵炎
- 膵嚢胞
- 肝がん
- 胆嚢がん
- 膵がん など
消化器内科で行う検査
消化器の病気を診断にあたっては、丁寧に問診をさせていただき、必要に応じて下記のような検査を行います。
血液検査
肝機能、膵臓の異常、炎症の有無、腫瘍マーカーなどを調べます。
胃内視鏡検査(胃カメラ)
口または鼻から細いカメラを挿入し、食道・胃・十二指腸の状態を観察します。潰瘍や炎症、がんの有無を調べ、必要に応じて組織を採取して検査します。
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)
肛門からカメラを挿入し、大腸の粘膜を観察します。ポリープやがん、炎症性腸疾患の有無を調べます。小さいポリープであれば切除します。
腹部超音波検査(エコー)
肝臓・胆のう・膵臓などの状態を超音波で調べます。脂肪肝や胆石、腫瘍の有無を確認します。
消化器内科で行う治療
消化器内科では、病気の原因や、患者様それぞれ症状に応じて適切な治療を行います。
主な治療法としては、まず薬物療法があります。使用する薬としては、胃酸を抑える薬、炎症を抑える薬、便秘や下痢を改善する薬、抗生物質、抗ウイルス薬などがあります。また、生活習慣改善の指導をさせていただくこともあります。消化器の病気は、生活習慣と深く関わっているものが多く、生活習慣を改善することで症状が軽減したり、悪化を防いだりできる疾患が少なくありません。指導の内容としては、食事内容の改善、運動の指導、禁酒・禁煙の指導、ストレス管理などがあります。
逆流性食道炎とは
逆流性食道炎は、胃酸が食道へ逆流し、食道の粘膜に炎症を引き起こす病気です。食道の粘膜は胃ほど強い酸に耐えられないため、逆流が続くと炎症が進行し、症状が悪化することがあります。放置すると食道の炎症が慢性化し、粘膜が傷ついて潰瘍ができることがあります。
また長期間にわたって強い炎症が続くと、食道がんのリスクが高まることが知られていますので、早めに治療することが大切です。
逆流性食道炎の症状
代表的な症状は胸やけと呑酸(口の中に酸っぱい液が上がってくる感覚)です。特に食後や横になったときに症状が出やすく、胃酸の逆流による刺激で食道や喉の違和感が生じます。慢性的な咳や声のかすれ、のどの違和感、胸の痛みを訴えることもあり、これらの症状は風邪や他の病気と勘違いされることがあります。
逆流性食道炎の原因
主な原因は、胃酸の分泌過多や、食道と胃の境目の筋肉の機能低下です。脂っこい食事やアルコール、カフェインの摂取、喫煙、過食が影響し、胃酸の分泌を増やしたり、胃の圧力を高めたりすることで症状が悪化します。肥満や妊娠も腹圧を上昇させるため、胃酸の逆流を招きやすくなります。また、加齢によって下部食道括約筋の働きが弱まると、逆流が起こりやすくなると考えられています。
逆流性食道炎の検査
診断には、症状の問診に加えて胃内視鏡検査(胃カメラ)が行われます。胃カメラでは、食道の粘膜に炎症や潰瘍がないかを直接確認し、必要に応じて組織を採取して詳しく調べます。症状があるにもかかわらず内視鏡検査で炎症が見られない場合は、食道の動きや胃酸の逆流を調べる検査を行うこともあります。
逆流性食道炎の治療法
治療の基本は、生活習慣の改善と薬物療法です。生活習慣の改善としては、脂っこい食事やアルコール、カフェインの摂取を控え、過食を避けることが大切です。また、食後すぐに横にならず、上半身を少し高くして寝ることで胃酸の逆流を防ぐことができます。このほか、タバコに含まれるニコチンが胃酸の分泌を促進し、食道と胃のつなぎ目の筋肉をゆるめるため、禁煙することが重要です。
薬物療法では、胃酸の分泌を抑える薬剤が使われます。これらの薬は胃酸の分泌を減らし、食道の炎症を改善する効果があります。胃の動きを良くする薬も補助的に用いられることがあります。重症の場合は、内視鏡や手術による治療が検討されることもあります。
ピロリ菌とは
ヘリコバクター・ピロリ菌は胃粘膜に生息し、胃炎を起こす細菌です。
胃潰瘍、十二指腸潰瘍の原因になります。一定期間感染が持続することで胃がんの原因にもなるため、早めの治療が必要です。
ヘリコバクター・ピロリ菌感染の症状
みぞおち辺りの痛みや食欲が出ないなど様々な消化器症状の原因になり得ます。胃潰瘍、十二指腸潰瘍ができたら腹痛だけではなく、出血した場合は黒色便、吐血をきたすことがあります。
ヘリコバクター・ピロリ菌感染の治療
胃酸分泌を抑える薬剤と2種類の抗生物質を1週間飲むことで90%以上の確率で除菌が成功します。
ヘリコバクター・ピロリ菌の検査
ヘリコバクター・ピロリ菌の診断には、血液検査(抗体検査)、尿素呼気試験、便中抗原が用いられます。
血液検査(抗体検査)
採血を行い、血液中のヘリコバクター・ピロリ菌抗体を測定します。ヘリコバクター・ピロリ菌への感染の有無、過去に感染していたかを調べる検査です。
尿素呼気試験
検査試薬を服用し、袋に息を入れて行う検査です。
便中抗原
便に含まれるヘリコバクター・ピロリ菌の抗原を検出します。