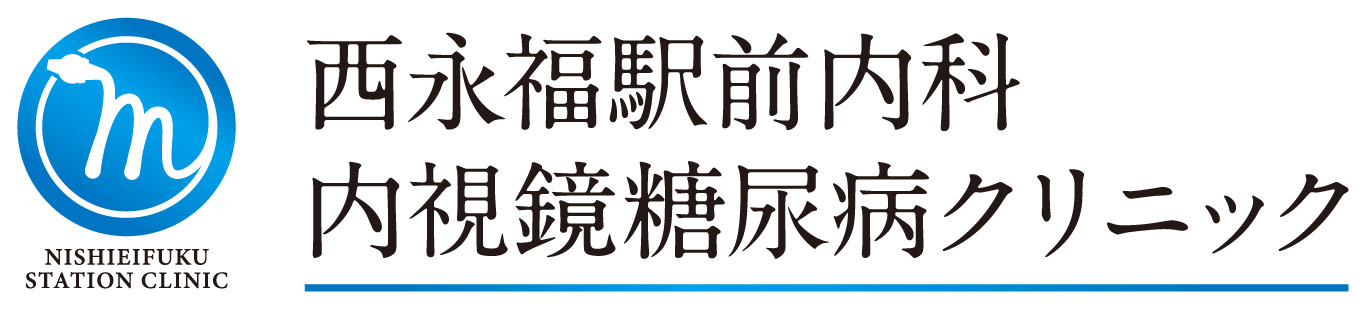生活習慣病とは

生活習慣病とは、日々の食生活や運動不足、喫煙、飲酒、ストレスなどが原因で発症する病気の総称です。代表的なものには、高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症(痛風)などがあります。これらは自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行します。放置していると合併症などを発症し、健康に深刻な影響を及ぼすため、早期の診断と適切な管理が重要になります。
当院では生活習慣病の不安をお持ちの患者様に対し、患者様それぞれの状態に合わせた生活習慣の見直しや指導、薬による治療などを行っていきます。それにより、血圧や血糖値などをコントロールして、合併症の発症の予防や進行の抑制を目指します。健康診断で異常を指摘された方、家族に生活習慣病の方がいる方、最近、お腹がポッコリ出てきた、血圧が高い、などと感じる方は、ぜひお早めにご相談ください。
生活習慣病の原因となる生活習慣
生活習慣病は、主に以下のような生活習慣が原因となります。
不適切な食生活
高カロリー・高脂肪の食事や塩分の多い食事が、肥満や高血圧の原因になります。また夜遅くに食事を摂ると血糖値が上がりやすく、糖尿病のリスクが高まるという報告もあります。
運動不足
運動不足はエネルギー消費の減少や筋肉量の減少で、肥満や血糖値の上昇を引き起こし、生活習慣病を悪化させます。
喫煙・過度な飲酒
タバコは含まれる有害物質によって血管を傷つけ、動脈硬化を進行させます。またアルコールの過剰摂取は高血圧や肝臓病のリスクを高めます。
ストレスや睡眠不足
ストレスを受けるとコルチゾールというホルモンが分泌され、血糖値が上がることが知られています。また血圧などにも悪影響を与え、生活習慣病を引き起こします。
高血圧症とは
高血圧症とは、血管にかかる圧力が慢性的に高くなる状態を指し、心臓や血管に大きな負担をかける病気です。血圧は、心臓が血液を全身に送り出す際に血管内で発生する圧力であり、通常は適正な範囲内に維持されていますが、高血圧の状態が続くと、血管が傷つき、さまざまな合併症を引き起こす危険性が高まります。自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行するため注意が必要です。
高血圧症の診断基準
高血圧症は、日本高血圧学会の基準に基づき、以下のように診断されます。
- 診察室血圧:収縮期血圧140mmHg以上 または 拡張期血圧90mmHg以上
- 家庭血圧:収縮期血圧135mmHg以上 または 拡張期血圧85mmHg以上
血圧は日々の生活や測定環境によって変動するため、一度の測定結果だけで判断せず、複数回の測定結果を基に診断します。
高血圧症を引き起こす原因
高血圧には、原因が特定できない「本態性高血圧」と、腎臓疾患や副腎疾患など特定の病気が原因で発症する「二次性高血圧」があります。高血圧症の90%以上が本態性高血圧で、遺伝的な要因に加え、生活習慣が深く関与していると考えられています。関わっている生活習慣としては塩分の過剰摂取(塩分を多く摂ると、体内の水分量が増え、血液量が増加して血圧が上がります)、肥満(内臓脂肪が増えると、血圧を上昇させるホルモンの分泌が活発になります)、運動不足、喫煙、過度の飲酒、ストレスなどが挙げられます。
高血圧症の症状
高血圧は、ほとんどの場合、自覚症状がありません。しかし、血圧が極端に高くなると、頭痛やめまい、動悸や息切れ、首や肩のこり、耳鳴りや視力のかすみなどの症状が現れる場合があります。また自覚症状が現れないからといって放置していると、血管に大きな負担がかかり続け、動脈硬化が引き起こされてしまいます。
動脈硬化とは、血管の壁が厚くなり、弾力を失い、血流が悪くなる状態です。動脈硬化は、脳卒中(脳梗塞・脳出血)、心筋梗塞・狭心症、腎不全、大動脈瘤・大動脈解離といった命に関わる重大な疾患の要因となるため、早期に高血圧への対策を取ることが、非常に重要になります。
高血圧症の治療
高血圧の治療は、生活習慣の改善と必要に応じた薬物療法が基本となります。生活習慣の改善としては、減塩(1日の塩分摂取量を6g未満に抑えることが推奨されます)、適度な運動(ウォーキングや軽いジョギングなど)、バランスの良い食事を摂り、体重管理をしていく(脂質の多い食事を控え、肥満を解消する)、禁煙、節酒、ストレスの軽減といったことに取り組んでいきます。
生活習慣だけでは血圧がコントロールできない場合、合併症のリスクがある場合は、薬による治療を検討します。使用する薬としては、体内の余分な水分や塩分を排出し血圧を下げる「利尿薬」、血管を広げ血圧を下げる「カルシウム拮抗薬」、血管を収縮させる物質の働きを抑える「ACE阻害薬」「ARB」、心臓の負担を軽減し血圧をコントロールする「β遮断薬」などがあります。これらを患者様に合わせて選択し処方します。
糖尿病とは
糖尿病とは、血液中のブドウ糖の値(血糖値)が慢性的に高くなる病気です。健康な人の体では、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンが血糖値を適切に調整しています。しかし、糖尿病になるとインスリンの働きが弱まったり、分泌量が不足したりすることで血糖値が高い状態が続きます。この状態が長く続くと、全身の血管や神経に障害を引き起こし、重篤な合併症の原因となります。
糖尿病の診断基準
糖尿病の診断は、以下の基準のうち1つ以上を満たした場合に行われます。
- 空腹時血糖値が126mg/dL以上
- 75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)2時間後の血糖値が200mg/dL以上
- 随時血糖値が200mg/dL以上
- HbA1c(ヘモグロビンA1c)が6.5%以上
いずれかの数値が異常であっても、再検査や医師の判断によって確定診断されます。健康診断などで血糖値が高めと言われた場合は、早めの受診をおすすめします。
糖尿病を引き起こす原因
糖尿病には主に「1型糖尿病」と「2型糖尿病」があります。1型糖尿病は自己免疫の異常により膵臓からのインスリン分泌がほぼ停止する疾患であり、幼少期から発症することが多くみられます。一方で、日本人の糖尿病の約95%を占めるのが2型糖尿病で、これは生活習慣と遺伝的要因が組み合わさって発症します。
2型糖尿病の主な原因としては、過食や不健康な食習慣(高カロリー・高脂肪の食事、糖分の過剰摂取)、運動不足、肥満(とくに内臓脂肪が多いとインスリンの効きが悪くなることが知られています)、遺伝的要因、ストレス(ホルモンバランスの乱れにより血糖値が上昇しやすくなる)などが挙げられています。
糖尿病の症状
初期の糖尿病は自覚症状がほとんどありません。しかし、血糖値の異常が進行すると、喉の異常な渇き、頻尿(とくに夜間)、体重の急な減少、体のだるさ・倦怠感、目のかすみ、傷が治りにくくなるといった症状が現れることがあります。こうした症状がある場合、すでに糖尿病が進行している可能性がありますので、早めの受診が大切です。
糖尿病の合併症について
糖尿病を放置すると、全身の血管や神経にダメージを与え、深刻な合併症を引き起こします。大きな血管では動脈硬化が加速することで、心筋梗塞や脳卒中など命に関わる疾患のリスクが高まります。また細小血管が障害されることで、糖尿病の三大合併症としてしられる以下の疾患が引き起こされることがあります。
糖尿病網膜症
高血糖が続くことで、眼の網膜の血管が傷つき、視力低下や最悪の場合失明につながることがあります。
糖尿病腎症
腎臓の毛細血管が損傷し、腎機能が低下。最終的には人工透析が必要になることもあります。
糖尿病神経障害
末梢神経が障害されることで、手足のしびれや痛み、感覚鈍麻などが起こります。悪化すると足の潰瘍や壊疽を引き起こし、下肢の切断が必要になる場合もあります。
糖尿病の治療法
糖尿病の治療は、生活習慣の改善が基本となります。病状に応じて薬物療法が追加されることもあります。生活習慣の改善では、まず食事療法が大切で、栄養バランスを考え、血糖値の急激な上昇を抑える食事を心がけます。糖質の摂取量を適切に管理し、野菜や食物繊維を多く摂ることが推奨されます。また肥満はインスリンの働きを阻害し、筋肉体質はインスリンの効きをよくすることが分かっていますので、有酸素運動(ウォーキングやジョギングなど)に加え、筋力トレーニングを取り入れ、適正な体重を目指していきます。ストレスを溜めないことも重要です。
生活習慣の改善だけでは血糖値のコントロールが難しい場合、薬による治療を検討します。使用する薬としては、インスリンの分泌を促進したり、糖の吸収を抑えたりする作用により血糖値を下げる「経口血糖降下薬」や、食欲を抑えたり、インスリンの分泌を促したりする働きがある「GLP-1受容体作動薬」などがあります。また1型糖尿病の患者様や2型でも膵臓から十分なインスリンが分泌されなくなっている患者様では、インスリン製剤を注射で補う治療を行います。
脂質異常症とは
脂質異常症とは、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)のバランスが崩れた状態を指します。血液中に必要以上の脂質が存在すると、血管内に蓄積され、動脈硬化を引き起こしやすくなります。脂質異常症は自覚症状がほとんどなく、健康診断で偶然発見されることが多いのですが、放置すると心筋梗塞や脳梗塞の原因となるため、早めの診断と治療が重要です。
脂質異常症の診断基準
脂質異常症は、血液検査で以下の数値に基づいて診断されます。
- LDL(悪玉)コレステロールが140mg/dL以上
- HDL(善玉)コレステロールが40mg/dL未満
- 中性脂肪(トリグリセリド)が150mg/dL以上
LDLコレステロールが高すぎると動脈硬化を進行させ、HDLコレステロールが低すぎると血管内の脂肪の除去が十分に行われず、血管が詰まりやすくなります。また中性脂肪はエネルギーとして消費しきれないと、肥満を引き起こします。
脂質異常症の原因
脂質異常症の主な原因には、遺伝的要因と生活習慣の乱れがあります。脂肪分の多い食事や過剰な糖分摂取は、LDLコレステロールや中性脂肪を増加させ、運動不足で身体を動かさないと脂質の代謝が低下し、LDLコレステロールが蓄積されやすくなります。内臓脂肪型肥満では中性脂肪が増えやすく、HDLコレステロールが低下します。
またタバコはHDLコレステロールを減少させ、アルコールの過剰摂取は中性脂肪を増加させることが知られています。ホルモンも影響していると考えられており、閉経後の女性はホルモンバランスの変化により、LDLコレステロールが上昇しやすいといわれています。
脂質異常症の症状
脂質異常症は、初期段階では自覚症状がほとんどありません。そのため、健康診断などで指摘されるまで気づかないことがほとんどです。進行して血流が悪くなると、場合によっては頭痛やめまい、胸の圧迫感や動悸、足の冷えやしびれなどが出ることもあります。
さらに放置してしまうと、動脈硬化が進行し、血管が狭くなったり詰まったりする「粥状動脈硬化」が起こります。これは、血管の内壁にコレステロールが蓄積し、プラーク(脂質の塊)を形成することで血流を妨げる状態です。粥状動脈硬化は、心筋梗塞や脳梗塞、閉塞性動脈硬化症(足の血流が悪化し、歩行時の痛みや潰瘍を引き起こす)など、重篤な合併症を引き起こす重大な要因になります。
粥状動脈硬化は長年にわたって進行するため、症状が現れたときにはすでに血管のダメージが大きくなっていることが多いです。そのため、早期診断と適切な治療が必要です。
脂質異常症の治療法
脂質異常症の治療は、主に生活習慣の改善と必要に応じた薬物療法を組み合わせて行います。食習慣の改善としては、脂肪分や糖分を控え、野菜や魚を積極的に摂取するようにすることが大切です。とくに青魚に含まれるDHAやEPAは、LDLコレステロールを低下させる効果があるとされています。
また運動習慣の改善として、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を積極的に行うことを心がけます。適度な運動により、HDLコレステロールが増加し、LDLコレステロールの排出の促進が期待できます。内臓脂肪を減らすことで、脂質の代謝も改善されます。また禁煙、節酒も重要になります。
生活習慣の改善だけでは改善が難しい場合、薬による治療も検討します。使用する薬としては、LDLコレステロールの合成を抑え、動脈硬化の進行を防ぐ「スタチン系薬」や、中性脂肪を減少させ、HDLコレステロールを増やす「フィブラート系薬」、腸でのコレステロール吸収を抑える「エゼチミブ」などがあります。
高尿酸血症とは
高尿酸血症とは、血液中の尿酸が過剰に増えた状態を指します。尿酸は、プリン体を分解したときに産出される、いわば老廃物です。プリン体は生物の細胞の中に含まれており、代謝や増殖などに関わっている重要な物質です。しかしプリン体を多く含む食物を摂り過ぎると、尿酸が排出され切らず、高尿酸血症を引き起こします。また腎臓における尿酸の排出機能が低下している場合も発症することがあり、その両方が原因の場合もあります。
血液中の尿酸値が高くなると、結晶化して関節や腎臓に蓄積します。これが進行すると、激しい痛みを伴う「痛風」や腎障害の原因となるため、適切な管理が必要です。
高尿酸血症の診断基準
血液検査で尿酸値が7.0mg/dL以上になると、高尿酸血症と診断されます。尿酸値がこの基準を超えてもすぐに症状が現れるわけではありませんが、長期間にわたって高い状態が放置され続けると、痛風や腎臓の病気を引き起こすリスクが高まります。
高尿酸血症を引き起こす原因
高尿酸血症の原因には、大きく分けて「尿酸の過剰産生」と「尿酸の排出低下」、その両方が混在するものがあります。過剰産生の原因としては、プリン体の多い食事(レバー、肉類、魚卵、ビールなど)が挙げられます。アルコールはプリン体ゼロと言われているものでも、尿酸の生成を促し、同時に排出を妨げるため、高尿酸血症の大きな原因となります。また内臓脂肪の蓄積は、尿酸産生を亢進するということや、インスリン抵抗性により尿酸の再吸収が促進され、尿酸排泄が低下するということが考えられています。加えて腎臓機能が低下すると、尿酸の排出能力が低下し、血中の尿酸値が高くなります。
高尿酸血症による症状
初期の高尿酸血症では、ほとんど自覚症状がありません。しかし、尿酸値が高い状態が続くと、体内に尿酸の結晶が沈着し、以下のような症状を引き起こします。
痛風発作
足の親指の付け根や足首、膝などの関節に突然激しい痛みと腫れが生じます。発作は数日から1週間程度続き、放置すると繰り返し発生します。
腎臓への影響
尿酸が腎臓に蓄積すると、尿路結石を形成し、尿管に詰まると、背中や腹部の激しい痛みや血尿を引き起こします。また腎機能の低下や腎不全のリスクを高めます。
関節の慢性炎症
長期的に尿酸結晶が沈着すると、関節や皮膚に痛風結節と呼ばれるコブができることがあります。さらに進行すると関節が変形し、慢性的な痛みや可動域の制限を引き起こします。
動脈硬化
高尿酸血症があると、動脈硬化のリスクが高いと考えられており、心筋梗塞や脳卒中の発症の危険があるため、注意が必要です。
高尿酸血症の治療法
高尿酸血症の治療は、生活習慣の改善を基本とし、必要に応じて薬物療法を行います。生活習慣の改善としては、プリン体を多く含む肉類、魚卵、レバー、ビールなどの飲食を控え、野菜や大豆製品を積極的に摂取するようにします。また過剰な飲酒も控えるようにしましょう。
生活習慣の改善だけでは尿酸値が下がらない場合、薬物療法を検討します。使用する尿酸降下薬としては、尿酸生成抑制薬(アロプリノール製剤、フェブキソスタット製剤など)や、尿酸排泄促進薬(ベンズブロマロン製剤など)があります。ただし、痛風発作時に薬によって急激に尿酸値を下げると、さらに痛風発作を誘発する場合があるため、慎重に投与する必要があります。
痛風発作時には、痛みや炎症を抑える抗炎症薬を使用します。これにはステロイドや非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)があります。なお、痛風の予防・治療薬としては、「コルヒチン」という薬剤もあります。